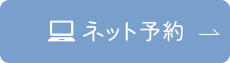胃もたれとは
 「胃もたれ」とは、胃の働きが一時的または慢性的に低下し、消化不良による不快感が生じる状態を指します。日常的に感じる軽い症状であることも多いですが、背景には機能性の異常だけでなく、胃や十二指腸の疾患が隠れているケースも少なくありません。
「胃もたれ」とは、胃の働きが一時的または慢性的に低下し、消化不良による不快感が生じる状態を指します。日常的に感じる軽い症状であることも多いですが、背景には機能性の異常だけでなく、胃や十二指腸の疾患が隠れているケースも少なくありません。
単なる「重い感じ」「張る感じ」として片づけられがちですが、実際には消化管運動の異常・胃酸分泌の異常・粘膜の炎症・精神的ストレスなど、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こるため、軽視せず原因を見極めることが大切です。原因を特定せずに市販薬だけでごまかしていると、病気の発見が遅れるリスクもあります。
不安な症状がある場合は、内視鏡検査などによる正確な診断を受けた上で、必要な治療や生活改善を行うことを心がけましょう。
胃もたれの受診の目安
放置してはいけないサイン
以下のような症状があれば、できるだけ早めに消化器内科を受診することが推奨されます。
- 胃もたれが1週間以上続く
- 吐血や黒色便が出る(消化管出血の可能性)
- 食欲不振・体重減少
- 市販薬で改善しない
- 前と違う強い胃痛や不快感がある
これらの症状がみられたら、なるべく早めに消化器内科を受診しましょう。
胃もたれの症状と特徴
胃部不快感・膨満感(ぼうまんかん)
胃のあたりが「重い」「つかえる」「張っている」と感じるのは、胃もたれでよく見られる症状です。医学的には「上腹部不快感」や「胃部膨満感」と呼ばれ、食後すぐや数時間後に強くなる傾向があります。
食べたあとも胃の中に何か残っているように感じたり、ガスがたまってげっぷやおならが増えたりすることもあります。これは、胃の動きが弱くなって食べ物の消化が進まず、胃の中に長くとどまってしまうためです。
また、胃酸の分泌が多すぎても少なすぎても、消化不良を起こして膨満感の原因になります。体質的に胃の内容物が逆流しやすい人(たとえば食道裂孔ヘルニアがある場合)では、胸のつかえ感を強く感じることもあります。 こうした症状が長引く場合は、単なる食べ過ぎではなく、胃の機能低下や病気の可能性もあるため、医療機関で相談してみましょう。
早期飽満感
「ほんの少ししか食べていないのに、すぐにお腹がいっぱいになってしまう」
こうした早い段階で満腹感を覚える状態は、「早期飽満感」と呼ばれ、特に女性や高齢者に多く見られます。食事を始めて数分でお腹がいっぱいになり、それ以上食べられなくなることが多く、飲み物ですら満腹に感じる場合もあります。
この背景には、胃が食事に合わせてふくらむ力(拡張性)が弱くなっていることがあり、特に機能性ディスペプシアなどの疾患でよく見られます。また、胃の働きをコントロールする自律神経(迷走神経)の機能が低下していると、胃が正しく拡張せず、少量の食事でも満腹と感じやすくなります。この状態が続くと、必要な栄養がとれなくなり、体力の低下や免疫力の低下、筋力の減少などにもつながるため、注意が必要です。
食欲低下
胃もたれが続くと、だんだんと食事をすること自体が億劫になり、自然と食欲が落ちてくることがあります。お腹はすいているはずなのに「食べたいと思えない」「食べる気になれない」という状態です。なかには「食べてもおいしく感じない」と訴える方もいます。
こうした食欲低下は、胃の中に食べ物が残っているような感覚や、食後の不快感が原因で起こることが多く、無意識のうちに「またあの不快な感じがするのでは」と食事を避けてしまうようになります。
背景には、胃の消化機能の低下に加えて、ストレスや自律神経の乱れが関係していることもあります。精神的な緊張や不安、軽度のうつ状態があると、脳の視床下部にある「食欲中枢」の働きが鈍り、食欲が自然と低下します。
また、注意したいのは、胃がんや膵がんなどの消化器系の病気でも、初期症状として食欲不振が現れることがあるという点です。特に、最近急に食が細くなった、体重が減ってきた、という場合には、早めに医療機関を受診することが大切です。
長く続く食欲低下は、栄養不足や体力の低下だけでなく、フレイルやサルコペニア(筋肉量の減少)など高齢者の健康リスクにも直結します。市販薬での対処に頼るだけでなく、原因を見極めたうえで適切な治療につなげることが重要です。
胃もたれと伴う吐き気や嘔吐
胃もたれに伴って現れることのある吐き気や嘔吐も、胃の動きが低下しているサインのひとつです。食後に「気持ち悪い」「むかむかする」と感じたり、場合によっては実際に嘔吐することもあります。空腹時に吐き気が出る場合は、胆汁の逆流やストレスの影響が関係していることも考えられます。
このような吐き気の原因としては、胃排出遅延(胃の内容物がなかなか腸へ送られない状態)や、胃の出口がむくんで狭くなる「幽門通過障害」などが考えられます。また、胃酸が過剰だったり、胆汁が胃に逆流することで、胃の粘膜が刺激され、吐き気を感じやすくなることもあります。
慢性的な吐き気が続く場合は、機能性ディスペプシアや胃潰瘍だけでなく、膵炎・胆石・腸閉塞など他の消化器疾患の可能性もあるため、自己判断で済ませず、医療機関での検査が必要です。
さまざまな症状が組み合わさっている
胃もたれの症状は単独で現れることもありますが、複数の症状が重なることが多いのが特徴です。
例えば、
- 「早期飽満感」と「胃部膨満感」が両方ある
- 「吐き気」がありつつ「食欲低下」もある
- 「胃の重さ」と「げっぷ」「おなら」が増える
このような場合、機能性ディスペプシアの可能性が高まる一方で、胃・十二指腸潰瘍や悪性疾患を除外するための精査も欠かせません。まずは一度、受診して診察を受けることをお勧めします。
胃もたれの原因
食生活の乱れ
- 脂っこい食事
→揚げ物・ラーメン・クリーム系料理など - アルコールの多飲
- 夜遅くの食事や早食い
胃のぜん動運動が低下し、食べ物が胃に長くとどまることで症状が出ます。
加齢や自律神経の乱れ
年齢を重ねると、胃の粘膜から分泌される消化液の量や、胃の内容物を送り出す運動機能が徐々に低下していきます。こうした加齢による変化は、胃もたれや消化不良を感じやすくなる原因のひとつです。
また、睡眠不足や仕事のストレス、人間関係の悩みなど、日常の精神的な負担も胃に大きく影響します。これらのストレスは自律神経のバランスを乱し、胃の働きを調整している迷走神経の機能が低下することで、胃の動きや分泌が鈍くなり、症状を悪化させることがあります。
胃腸の病気
- 慢性胃炎:ピロリ菌感染や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)による粘膜障害です。
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍:胃酸と粘膜のバランスが崩れることで、潰瘍形成や痛みを伴います。
- 胃がん:特に早期胃がんでは自覚症状が少なく、胃もたれや違和感だけのケースもあります。
- 機能性ディスペプシア(FD):内視鏡検査などで異常が見つからないにも関わらず、胃もたれ・胃痛・早期飽満感などが続く慢性疾患です。
薬の副作用
NSAIDs、鉄剤、抗菌薬、ステロイド薬などは胃粘膜を傷つけたり、胃酸を増やしたりして、胃もたれの原因になります。