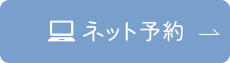吐き気・嘔吐とは
吐き気(悪心)とは、胃の内容物がこみ上げてくるような不快感を指します。実際に吐くわけではありませんが、嘔吐を伴うこともあります。一方、嘔吐とは、胃や腸の内容物が口から外へ排出される現象のことを指します。吐き気は嘔吐の前兆として現れることが多く、必ずしも嘔吐に至るわけではありません。
吐き気や嘔吐は、単なる胃の不調だけでなく、消化器疾患や神経系、内分泌系、感染症など、さまざまな病気の症状として現れることがあります。そのため、原因を特定し、適切な対応をすることが重要です。
緊急受診が必要な症状
- 吐血・コーヒーかす状の嘔吐 → 消化管出血(胃潰瘍・食道静脈瘤破裂)
- 激しい頭痛・意識障害 → 脳出血・くも膜下出血
- 持続的な腹痛・黄疸 → 急性膵炎・胆管炎
- 高熱・下痢を伴う → 感染性胃腸炎・敗血症
- 頻回の嘔吐で水分摂取不可 → 脱水症
吐き気・嘔吐と合わせて上記のような症状がみられる方は、速やかに受診してください。場合によっては救急車を呼ぶという判断が必要です。
吐き気のメカニズム
吐き気は、さまざまな要因によって引き起こされます。主な発生経路は4つあり、それぞれの仕組みと代表的な原因を紹介します。
- 消化管の異常によるもの(消化管由来)
胃や小腸の粘膜が刺激を受けると、迷走神経を介して嘔吐中枢へ信号が送られ、吐き気が生じます。
主な原因:食中毒、胃腸炎、胃潰瘍 - 脳の異常によるもの(中枢神経系由来)
延髄にある嘔吐中枢が直接刺激を受けることで、吐き気が発生します。
主な原因:片頭痛、脳圧亢進(脳腫瘍・くも膜下出血など) - 耳の異常によるもの(前庭系由来)
耳の内耳にある「前庭器官」が異常な刺激を受けると、脳に信号が伝わり、吐き気を引き起こします。
主な原因:メニエール病、乗り物酔い - ホルモンや代謝の異常によるもの(内分泌・代謝異常由来)
血液中のホルモンや代謝産物のバランスが崩れることで、吐き気が生じます。
主な原因:妊娠(つわり)、尿毒症、低血糖
吐き気は単なる胃の不調だけでなく、脳や耳、ホルモンバランスの乱れなど、さまざまな要因で起こるため、原因に応じた適切な対処が重要です。
嘔吐のメカニズム
嘔吐は、いくつかの段階を経て発生します。それぞれのステップを分かりやすく解説します。
- 嘔吐の前兆(前駆期)
吐き気(悪心)を感じ、冷や汗や唾液の分泌が増加します。この段階では、迷走神経や交感神経が関与し、体が嘔吐に備え始めます。 - 嘔吐の準備(準備期)
体が胃の内容物を排出しやすい状態に整えます。
• 横隔膜が収縮 → 胃の圧力が上昇
• 食道下部の括約筋が弛緩 → 胃の内容物が逆流しやすくなる
• 腹筋が収縮 → 胃を圧迫し、内容物を押し出す - 嘔吐の実行(排出期)
最終的に口が開き、咽頭反射とともに胃の内容物が排出されます。これにより、体が不要なものを素早く外へ出します。
嘔吐は体の防御反応の一つであり、異物の排出や消化器の異常を示す重要なサインでもあります。
吐き気・嘔吐の原因
吐き気・嘔吐はさまざまな要因で起こりますが、ここでは当院の専門である消化器系の視点から解説します。
1. 胃腸炎(ウイルス性・細菌性)
胃腸炎は、ウイルスや細菌の感染により胃や腸の粘膜に炎症が起こる疾患です。急激に発症し、吐き気・嘔吐・下痢・腹痛・発熱などの症状を伴うことが多いのが特徴です。
- ウイルス性胃腸炎
• 原因ウイルス:ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど
• 感染経路:飛沫感染、接触感染、食品を介した経口感染
ノロウイルス(冬に多い):激しい嘔吐と水様性の下痢を伴う。感染力が強く、家族内・施設内で集団感染を引き起こしやすい。
ロタウイルス(乳幼児に多い):白色または灰白色の下痢便が特徴。高熱や脱水を引き起こしやすい。 - 細菌性胃腸炎
• 原因菌:サルモネラ菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌(O157など)、黄色ブドウ球菌
• 感染経路:生肉・生魚、未加熱の食品、汚染された水
カンピロバクター:鶏肉由来が多く、摂取後1〜7日で発症。腹痛と水様性下痢が長引く。
O157:溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすことがあり、重篤化する可能性がある。
2. 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃潰瘍・十二指腸潰瘍は、胃酸やピロリ菌などの影響で胃や十二指腸の粘膜が傷つく疾患です。粘膜の防御機能が低下し、胃酸の攻撃を受けることで、炎症や潰瘍(粘膜の深い傷)が発生します。
原因
- ピロリ菌感染(慢性的な炎症を引き起こす)
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)(ロキソニンなどの痛み止めによる粘膜障害)
- ストレス(胃酸分泌の増加)
- 喫煙・アルコール(粘膜の血流を悪化させる)
症状
- 胃潰瘍:食後にみぞおちが痛むことが多い(胃酸が食べ物と混ざることで刺激を受ける)。
- 十二指腸潰瘍:空腹時に痛みが出やすい(胃酸が直接粘膜を刺激する)。
- 吐き気・嘔吐:胃の運動が低下し、内容物の排出がうまくいかないため。
- 吐血・黒色便:潰瘍からの出血により、コーヒーかす状の嘔吐や黒色便が見られることがある。
3. 胆石症・胆嚢炎
胆石症は、胆のう内にできた胆石(コレステロールやカルシウムを含む結石)が胆汁の流れを妨げる疾患です。胆嚢炎は、胆石による炎症や細菌感染が加わった状態を指します。
原因
- 胆汁の成分異常(コレステロールの過剰沈着)
- 嚢の運動低下(胆汁の排出不良)
- 脂質の多い食事(胆汁分泌の負担増)
症状
- 右上腹部の痛み(特に脂っこい食事の後に悪化)
- 吐き気・嘔吐(胆汁の流れが滞ることで消化がうまくいかない)
- 黄疸(胆管が詰まると、胆汁の流れが阻害されて皮膚や目が黄色くなる)
- 発熱・悪寒(細菌感染を伴う場合)
4. 腸閉塞(イレウス)
腸閉塞は、腸の内容物が通過できなくなる病態です。完全閉塞(まったく通らない)と、不完全閉塞(部分的に通る)に分かれます。
原因
- 機械的イレウス 腸が物理的に塞がる(腫瘍、術後の癒着、ヘルニアなど)
- 機能的イレウス 腸の運動が低下し、内容物を送り出せない(麻痺性イレウス)
症状
- 吐き気・嘔吐(食べたものが腸を通過できず逆流する)
- 腹部膨満感(腸の中にガスや液体がたまり、膨れる)
- 便秘・ガスが出ない(完全閉塞の場合)
- 腹痛(特に間欠的に強くなることが特徴)
胃腸炎は、ウイルスや細菌の感染が原因となり、吐き気や嘔吐、下痢が主な症状として現れます。胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、胃酸の影響で粘膜が傷つくことで、吐き気や腹痛を引き起こします。胆石症や胆嚢炎では、胆汁の流れが滞ることにより、吐き気や嘔吐、右上腹部の痛みが生じます。腸閉塞の場合は、腸が詰まることで内容物が通過できず、嘔吐や腹部の膨満感が現れます。 以上のように、吐き気や嘔吐の原因はさまざまなため、症状が続く場合は早めに医療機関を受診することが大切です。
吐き気・嘔吐への対応方法
1. 食事を控える
嘔吐直後は、胃が敏感な状態になっており、無理に食事をすると再び吐いてしまうことがあります。そのため、嘔吐後は2~3時間ほど何も食べずに胃を休めることが望ましいです。特に、油っこい食べ物や消化の悪いものは避ける必要があります。食事を再開する際は、まずはおかゆやスープなど消化に良いものを少量ずつ摂取するとよいでしょう。
2. 水分補給
嘔吐によって体内の水分が失われるため、脱水を防ぐためにこまめな水分補給が必要です。ただし、一度に大量の水を飲むと嘔吐を誘発することがあるため、経口補水液やスポーツドリンクを少量ずつ摂取することが大切です。水分補給の際は、冷たいものよりも常温のものが胃に優しく、負担がかかりにくいです。
3. 安静にする
嘔吐後は、体が疲労し、自律神経のバランスも乱れがちになります。横になって休むことが重要ですが、完全に仰向けで寝ると胃酸が逆流しやすくなるため、上半身を少し起こした姿勢をとるのが理想的です。また、リラックスすることで自律神経が整い、吐き気が軽減されることもあります。
4. 吐き気止め(制吐剤)の使用
吐き気が強い場合は、メトクロプラミドやドンペリドンといった制吐剤が有効です。これらの薬は、胃の動きを改善し、吐き気を抑える効果があります。ただし、持病がある方や妊娠中の方は、使用に注意が必要な場合があるため、自己判断せずに医師の指示を仰ぐことが大切です。
早めの受診が必要なケース
吐き気や嘔吐が長引く場合や、次のような症状を伴う場合は、消化器内科を受診することが重要です。
- 頻回の嘔吐で水分補給ができない(脱水症のリスク)
- 吐血やコーヒーかす状の嘔吐がある(消化管出血の可能性)
- 激しい腹痛や発熱を伴う(胃腸炎や胆嚢炎の疑い)
- 頭痛やめまい、意識障害を伴う(脳出血や髄膜炎の可能性) 嘔吐は体の防御反応の一つですが、原因によっては放置すると危険な場合もあります。症状が続くときは、早めに医療機関を受診しましょう。