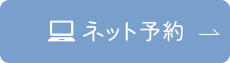過敏性腸症候群とは
過敏性腸症候群(IBS: Irritable Bowel Syndrome)は、消化器内科でよく見られる機能性消化管障害の一つです。これは、腸の形態的異常がないにもかかわらず、慢性的な腹痛や腹部不快感とともに排便習慣の変化(下痢、便秘、またはその両方)が繰り返し起こる疾患です。
過敏性腸症候群の有病率は、先進国で10〜20%程度とされており、特に20〜40代での発症が多く、女性にやや多い傾向があります。男女差がある理由として、ホルモンバランスの違いや、女性のほうがストレスへの感受性が高い可能性が挙げられます。また、発症年齢に関しては、ストレスフルな社会生活が始まる成人初期に多く見られます。
過敏性腸症候群は慢性的な疾患ですが、生活習慣や治療の工夫により症状をコントロールできます。
- 食事やストレス管理が重要です。特に低FODMAP食や腸内細菌改善を含むアプローチが効果的です。食事の内容やタイミングにも注意を払い、規則正しい食生活を心がけましょう。
- 適度な運動は、腸の蠕動運動を促進するだけでなく、ストレスを軽減する効果もあります。
- 患者さん一人ひとりに合った治療計画を医師と一緒に探していきましょう。どの治療法が最適かは個人差があるため、定期的な診察と調整が重要です。
具体的な症状や治療計画の相談があれば、ぜひ医療機関へお越しください。
過敏性腸症候群の症状
お腹の症状
- 急な腹痛や便意が生じて下痢になることが多い。
- 緊張やプレッシャーを感じると腹痛が起こりやすい。
- 大切な場面やトイレに行けない状況で腹痛を感じやすくなる。
- 外出先で突然の便意に襲われ、下痢になることがある。
- 腹痛は排便後に軽減することがある。
- 「急にお腹が痛くなったらどうしよう」という不安から、外出や重要な用事が心配になる。
- 下痢と便秘を繰り返す。
- 緊張やストレスによって便秘になりやすい。
- 便秘の際、コロコロとした硬い便が出る。
- ガスが溜まり、お腹が張って苦しい感覚がある。
お腹以外の体の症状
- みぞおち付近の痛み。
- 食欲の低下。
- 頭痛やめまい。
- 動悸が起こることがある。
- 頻尿や尿意を感じやすい。
- 筋肉痛を伴うことがある。
- 疲れやすさや倦怠感を感じる。
過敏性腸症候群の
種類別症状
過敏性腸症候群(IBS)は主に以下の4つの種類に分類され、それぞれ異なる症状を呈します:
1.下痢型(IBS-D)
- 主症状は、頻繁な水様便や軟便、突然の強い便意です。
- 腹痛は排便後に軽減することが多いですが、便意を我慢することが難しいため、外出先での不安が強まることがあります。
- ガスの増加や腹部膨満感も伴うことがあります。
2.便秘型(IBS-C)
- 硬い便やウサギの糞のようなコロコロした便が特徴です。
- 排便困難や排便後の残便感が強く、トイレに長時間こもることがあります。
- 腹痛や腹部の張りが日常的に見られます。
3.混合型(IBS-M)
- 下痢と便秘が交互に現れるタイプで、症状が一定せず、予測が難しいのが特徴です。
- 腹痛の強さや発生頻度も人によって異なります。
- 症状の変動により、生活の質が大きく影響を受けやすいです。
4.分類不能型(IBS-U)
- 便性状や排便パターンが上記のいずれにも該当しない場合、このタイプに分類されます。
- 症状の頻度や重症度は個人差が大きいです。
過敏性腸症候群の原因
病態メカニズム
過敏性腸症候群(IBS)の病態には以下の要因が関与していると考えられています:
- 腸管運動の異常
腸の蠕動運動が過剰になることで下痢を引き起こし、逆に運動が低下すると便秘を生じます。この調整不全は、腸の筋層の反応性の異常によるものと考えられています。また、腸内でのガスの蓄積や腸管の膨張による痛みも関連しています。 - 内臓知覚過敏
腸の感覚が過敏になり、通常では痛みを感じない刺激(食事や腸内ガスの移動など)にも敏感に反応します。この現象は、脳が腸からの信号を過剰に認識することが原因とされています。MRIを用いた研究では、IBS患者さんの脳内における痛みの処理領域が過剰に活性化していることが確認されています。 - 腸内細菌叢の変化
腸内フローラのバランスが乱れると、特定の細菌が過剰に増殖し、ガスの生成や腸の炎症を引き起こします。最近の研究では、腸内細菌由来の代謝物質であるトリプタミンとフェネチルアミンが、インスリン抵抗性や代謝症候群に関与する可能性が指摘されています。これにより、IBSが単なる腸の疾患ではなく、全身性の代謝異常と関連することが示唆されています。 - 脳腸相関の異常
腸と脳の間の神経ネットワーク(腸脳軸)の過敏性により、ストレスや感情的刺激が腸の運動や感覚に大きく影響します。このメカニズムは、心理的ストレスが症状を悪化させる主要な要因です。また、セロトニンなどの神経伝達物質の異常が関与していることがわかっています。 - 心理的ストレス
ストレスや不安、うつ病などの心理的問題がIBSの引き金となることが多いです。また、ストレスにより腸内の炎症が増加することも報告されています。特に幼少期のトラウマや心理的な負荷がIBSの発症リスクを高める要因となることが示唆されています。
過敏性腸症候群の検査診断
過敏性腸症候群(IBS)の診断には現在Rome IV基準が用いられています。この基準に基づき、慢性的な腹痛や排便習慣の変化が評価されます。IBSの診断には、問診だけでなく除外診断が重要です。具体的には大腸がんや炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)を除外するための検査が行われます。これには血液検査、便潜血検査、内視鏡検査が含まれます。
検査方法
IBSの診断には他の疾患を除外することが重要で、以下の検査が行われます:
- 問診と症状の評価 医師が患者さんの症状の経過や特徴を詳細に聴取します。特に、腹痛と排便習慣の関係、症状が生活に与える影響について確認します。
- 血液検査 炎症性疾患や感染症を除外するために行います。特に、C反応性タンパク(CRP)や白血球数の増加がないかを確認します。
- 便検査
・便潜血検査:消化管出血の有無を調べ、大腸がんやポリープの可能性を除外します。
・便中カルプロテクチン測定:腸管の炎症マーカーを評価し、炎症性腸疾患(IBD)との鑑別に用います。
・寄生虫検査:海外旅行歴がある場合などに寄生虫感染を確認します。 - 内視鏡検査大腸内視鏡(コロノスコピー)は、大腸がんや炎症性疾患の有無を確認するために行われます。特に50歳以上や赤血便がある場合には重要です。
- 画像診断腹部超音波やCT検査を用いて、腫瘍や腸管の構造異常を調べます。超音波は非侵襲的であり、腸管の動きや血流も観察できます。
- 腸内細菌叢解析腸内フローラのバランスがIBSの症状と関連しているため、腸内細菌叢を調べる検査が行われることがあります。これにより、個別化されたプロバイオティクス療法の可能性を評価します。
- 呼気試験ラクターゼ不足や小腸内細菌異常増殖(SIBO)の診断に用います。呼気中の水素やメタンの濃度を測定し、消化吸収不良や腸内発酵の異常を特定します。
- 心理的評価ストレスや不安、うつ病がIBSに強く関連しているため、必要に応じて心理的評価や精神科的サポートを受けることが推奨されます。
過敏性腸症候群の治療法
薬物療法
症状に応じて以下の薬剤が使用されます:
- 下痢型(IBS-D):ラモセトロン(5-HT3拮抗薬)は腸の運動を抑制し、下痢や腹痛を軽減します。また、リファキシミンのような抗菌薬も、腸内細菌のバランスを整えることで下痢型の改善に有効です。
- 便秘型(IBS-C):リナクロチドやルビプロストンは、腸管の分泌を促進し、便を柔らかくして排便を容易にします。新しい選択肢として、プレカナチドも効果が報告されています。
- 腹痛:トリメブチン(腸管運動調整薬)は、腸の過剰な収縮を抑制し、腹痛を軽減します。さらに、抗けいれん薬や低用量の三環系抗うつ薬(例:アミトリプチリン)は、痛みに対する感受性を低下させる効果があります。
さらに、プロバイオティクスの使用も症状の改善に寄与します。特定の菌株(ビフィズス菌BB12やラクトバチルス菌GGなど)が効果的であるとされています。
食事療法
- 低FODMAP食:特定の短鎖炭水化物を制限することで、腹痛、下痢、ガスの発生を軽減します。このアプローチには厳密な食事計画が必要であり、栄養士との相談が推奨されます。具体的な制限食品としては、リンゴ、牛乳、玉ねぎなどが含まれます。
- プロバイオティクス:特定の腸内細菌(ビフィズス菌やラクトバチルス)の補充が、腸内フローラを改善し、炎症を抑制します。
- 食物繊維:便秘型の患者さんには可溶性繊維(オオバコなど)が推奨される一方、下痢型の患者さんには不溶性繊維の摂取を控えることが重要です。
心理的アプローチ
認知行動療法(CBT):心理的ストレスを緩和し、脳腸相関を正常化します。特にストレスが症状を引き起こす患者さんには効果的です。
マインドフルネス:呼吸法や瞑想を通じてリラクゼーションを促し、症状の緩和に役立ちます。これにより、患者さんが自己管理能力を高めることが期待されます。
※必要と判断した際は、専門の医療機関をご紹介させていただきます。
過敏性腸症候群の予防
過敏性腸症候群(IBS)の予防には生活習慣の見直しやストレス管理が重要です。
1. バランスの良い食事
個人差がありますので、医師の指示に従って実践しましょう。
- 食物繊維を適切に摂取する:
可溶性食物繊維(オートミール、リンゴ、ニンジンなど)は便秘型IBSに効果的です。
一方で、不溶性食物繊維(全粒穀物、野菜など)は下痢型IBSの悪化を避けるため控えめにする必要があります。 - 低FODMAP食を試す:
消化されにくい炭水化物(乳糖、フルクトースなど)の摂取を制限することで症状を軽減します。また、アルコール、カフェイン、脂肪分の多い食品は症状を悪化させる可能性がありますので注意しましょう。
2. ストレス管理
- リラクゼーション法:
- スケジュール管理:
日々の生活のなかで、過密なスケジュールを避け、十分な休息時間を確保することが重要です。瞑想、深呼吸、ヨガなどのリラクゼーションテクニックは、脳腸相関を改善します。
必要に応じて認知行動療法(CBT)やカウンセリングを受けることで、不安やストレスを軽減できる場合があります。
3. 適度な運動
定期的な軽い運動(ウォーキング、ストレッチなど)は腸の運動を正常化し、ストレスを軽減します。過度な運動は逆効果となる場合があるため、適度な運動量を心がけましょう。
4. 規則正しい生活習慣
- 食事時間を一定に保つ:
毎日同じ時間に食事を摂ることで、腸のリズムが整います。 - 十分な睡眠を確保する:
睡眠不足はストレスを増加させ、IBSの症状を悪化させる可能性があります。 - 水分補給をしっかりと行う:
特に便秘型の患者さんには水分摂取が重要です。 - 腸内環境の改善
個人差がありますので、医師の指示に従って実践しましょう。
プロバイオティクス(乳酸菌、ビフィズス菌など)の摂取により、腸内細菌のバランスを改善し、症状を予防する可能性があります。発酵食品(ヨーグルト、キムチ、味噌など)の摂取も有効です。
5. 腸内環境の改善
※ 個人差がありますので、医師の指示に従って実践しましょう。
プロバイオティクス(乳酸菌、ビフィズス菌など)の摂取により、腸内細菌のバランスを改善し、症状を予防する可能性があります。発酵食品(ヨーグルト、キムチ、味噌など)の摂取も有効です。