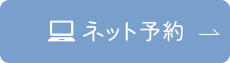ピロリ菌感染症とは
ピロリ菌感染症とは、胃の中に「ヘリコバクター・ピロリ菌」という細菌が感染し、胃の粘膜に慢性的な炎症を引き起こす病気です。この菌はらせん状の形状を持ち、鞭毛を使って胃粘膜を侵食します。ピロリ菌は、胃粘液層を突破して粘膜表面に定着し、そこから炎症を引き起こします。この菌が分泌するウレアーゼという酵素は、胃酸を中和して自分の生存環境を整えます。その結果、胃粘膜がダメージを受け、時間の経過とともにさまざまな疾患のリスクが高まります。特に慢性胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんなどの重篤な病気との関連性が確認されています。
ピロリ菌感染症は非常に広く見られ、特に衛生状態が十分に整っていない地域では感染率が高い傾向にあります。日本では、50歳以上の人々で感染率が高いことが知られていますが、近年は衛生環境の改善により若年層の感染率は低下しています。
ピロリ菌の感染経路
ピロリ菌は主に幼少期に感染することが多いとされています。その理由として、幼少期には胃酸の分泌量が少なく、菌が定着しやすい環境が整っていることが挙げられます。主な感染経路は以下の通りです:
- 家庭内感染
ピロリ菌は、家族内で共有される食器や調理器具、食べ物を介して感染することが最も多いです。例えば、親が噛み砕いた食べ物を子どもに与えたり、箸やスプーンを共有したりする行為がリスクを高めます。特に、感染した親がいる家庭では子どもの感染率が高いことが報告されています。 - 汚染された飲料水や食品
衛生環境が十分でない地域では、汚染された飲料水や食品が感染の原因となります。このため、発展途上国では感染率が非常に高い傾向があります。日本においても、戦後の衛生環境が不十分だった時代に多くの人々が感染したと考えられています。 - 唾液を介した感染
口腔内に存在するピロリ菌が唾液を介して感染する可能性があります。これは、飲み物や食べ物を共有した場合、またはキスなどを通じて感染するケースです。
ピロリ菌に感染すると、治療をしない限り長期間胃内に留まるため、将来的に胃の疾患を引き起こすリスクが高まります。感染の有無を確認し、適切な対応を取ることが重要です。
ピロリ菌感染が引き起こす病気
ピロリ菌感染は、胃の粘膜に慢性的な炎症をもたらし、以下のような疾患を引き起こす可能性があります。
- 慢性胃炎
ピロリ菌感染の最初の段階で現れる症状が慢性胃炎です。これは胃粘膜が炎症を起こし、胃の内壁が徐々に荒れる状態です。初期には自覚症状が乏しい場合が多いですが、放置すると粘膜が薄くなり、胃潰瘍や胃がんのリスクが高まります。 - 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
ピロリ菌感染が進行すると、胃粘膜のバリア機能が弱まり、胃酸が直接粘膜を攻撃します。これにより、胃や十二指腸の壁に深い傷が形成されます。胃潰瘍の典型的な症状には、食後の胃痛や胸やけ、吐き気があります。重症の場合、出血や穿孔といった合併症を引き起こすこともあります。 - 胃がん
ピロリ菌は胃がんの最大のリスク因子とされています。長期間にわたり胃粘膜が炎症を受けることで、萎縮性胃炎や腸上皮化生(胃粘膜が腸のような性質を持つ状態)を引き起こし、がん化のリスクが高まります。WHO(世界保健機関)はピロリ菌を発がん性物質として分類しています。 - 胃MALTリンパ腫
ピロリ菌感染が原因となるリンパ腫の一種です。この疾患は比較的まれですが、除菌治療を行うことで腫瘍が縮小し、完全に治癒する場合があります。
ピロリ菌検査
ピロリ菌感染を確認するためには、以下の検査が行われます。
- 尿素呼気試験
患者さんが尿素を含む試薬を服用し、呼気中に含まれる二酸化炭素の量を測定します。ピロリ菌がウレアーゼを分泌して尿素を分解するため、陽性の場合は特定のガス成分が増加します。この検査は非侵襲的で痛みがなく、簡便に実施できます。 - 便中抗原検査
便に含まれるピロリ菌の抗原を検出する方法です。感染の有無を調べるだけでなく、除菌治療後の効果確認にも利用されます。簡便で精度が高い検査として広く用いられています。 - 胃内視鏡検査(胃カメラ)
胃内視鏡を使用して胃粘膜の状態を直接観察し、必要に応じて粘膜を採取してピロリ菌を検出します。この方法は粘膜の炎症や潰瘍の状態を詳しく調べることができるため、病気の進行度を評価する上で非常に有用です。
ピロリ菌の治療法
ピロリ菌感染症の治療は、感染した菌を除去することを目的とした「除菌治療」です。通常、2種類の抗生物質(例:アモキシシリンとクラリスロマイシン)とプロトンポンプ阻害薬(PPI)を組み合わせた治療が行われます。また、治療後には再検査を行い、菌が完全に除去されたことを確認することが推奨されます。
- 治療の仕組み
抗生物質がピロリ菌を直接殺菌し、PPIが胃酸分泌を抑制して胃内のpHを上昇させます。これにより、抗生物質の効果が最大限に発揮される環境が整います。 - 治療の期間と成功率
治療期間は7日から14日間で、初回の成功率は90%以上と高いものの、近年では抗生物質に耐性を持つ菌の増加が課題となっています。耐性菌に対しては、別の種類の抗生物質を用いた再治療が検討されます。 - 注意点
除菌療法を完了した後は、ピロリ菌が完全に除去されたことを確認するための検査(呼気検査や便検査)が行われます。また、副作用として軽い下痢や味覚異常が起こることがありますが、多くの場合は一過性で問題ありません。
ピロリ菌感染の予防と早期発見の重要性
ピロリ菌感染を完全に防ぐことは難しいですが、以下の方法で感染リスクを下げることができます。
- 衛生的な生活習慣の徹底:手洗いや調理器具の清潔を心がける。
- 家庭内での食器や箸の共有を避ける。
- 清潔な飲料水や食品を摂取する。
さらに、家族内に胃がんの既往歴がある場合や、胃の不調が続く場合には、早期に検査を受けることが重要です。ピロリ菌の早期発見と治療により、将来的な疾患リスクを大幅に減らすことができます。
また、ピロリ菌除菌後も、胃がんのリスクは完全にはなくならないため、定期的な胃カメラ検査が重要です胃の健康を守るためにも、定期的な胃検診を心がけましょう。