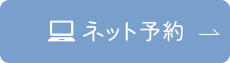機能性ディスペプシアとは
どんな病気?
機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia, FD)は、胃や十二指腸に明らかな器質的異常がないにもかかわらず、慢性的な上腹部の不快症状が続く病気です。
消化器疾患の中で比較的多い病気ですが、命に関わるものではありません。しかし、症状が長引くことで「食べる楽しさ」などを奪い、生活の質(QOL)を大きく低下させることもある病気です。
機能性ディスペプシアは日本人の約10人に1人が罹患する可能性があり、新たな国民病として注目されています。症状が続く場合は、日常生活に支障をきたす前に、消化器内科を受診して適切な診断と治療を受けることが大切です。
機能性ディスペプシアの
定義と種類
機能性ディスペプシアは、ローマIV基準という国際診断基準に基づいて診断されます。この基準では、以下の2つのタイプに分類されます:
- 食後愁訴症候群(PDS: Postprandial Distress Syndrome)
主に食後の胃もたれや早期満腹感が特徴です。胃の運動機能障害が関与していると考えられています。 - 心窩部痛症候群(EPS: Epigastric Pain Syndrome)
主にみぞおちの痛みや焼けるような感覚が中心です。胃酸や知覚過敏が関与している場合が多いです。
これらの症状が混在することもあり、患者によって症状の現れ方が異なります。
機能性ディスペプシアの
主な症状
- 胃もたれ(胃の排出遅延)
胃の運動機能障害により、食べた物が胃から十二指腸へ適切に送られないことで起こります。これにより、胃が重く感じたり、膨らんだような不快感が続きます。 - 早期満腹感
少量の食事で満腹感を感じるのは、胃の「適応性弛緩」という機能が低下しているためです。通常、食事を摂ると胃は膨らむ余裕を作りますが、この機能が弱いと胃がすぐにいっぱいだと認識します。 - 心窩部痛や灼熱感
胃や十二指腸の粘膜に異常がないにもかかわらず、わずかな刺激でも痛みや不快感を感じる「内臓知覚過敏」が関与しています。
機能性ディスペプシアの原因
機能性ディスペプシアの原因は一つに絞れませんが、以下の要因が複合的に絡み合っているとされています:
- 胃の運動機能障害
胃の収縮や内容物を排出する能力が低下し、胃もたれや食後の不快感を引き起こします。 - 内臓知覚過敏
胃や十二指腸の内部の圧力や刺激に対する感受性が高まることで、少しの膨張や胃酸による刺激を痛みとして感じます。 - ストレスと自律神経の乱れ
ストレスにより、胃の働きを調節する自律神経系が乱れ、胃の運動や酸分泌が異常をきたします。 - 胃酸の分泌異常
酸の分泌量が増加するだけでなく、正常範囲内の酸でも過敏に反応する場合があります。 - ピロリ菌感染
ピロリ菌による胃の慢性的な刺激が、知覚過敏や胃の運動異常を引き起こす可能性があります。 - 食生活や生活習慣
・脂っこい食事や早食いが胃の負担を増加させます。
・規則な食事時間や過食も症状を悪化させる要因です。 - 心理的要因
うつ病や不安障害がある場合、症状が強く現れることが知られています。
特に現代社会のストレス、特に職場での人間関係、金銭面での不安、将来に対する漠然とした不安が機能性ディスペプシアの増加に関連していると考えられています。
機能性ディスペプシアの
診断方法
機能性ディスペプシアの診断には、他の疾患を除外することが不可欠です。特に胃がんや胃潰瘍、胆石症などとの鑑別が重要です。
診断の手順
1問診と症状の確認
症状の持続期間(6ヶ月以上前から、直近3ヶ月間持続)が確認されます。
2内視鏡検査
胃や十二指腸の炎症、潰瘍、腫瘍などの器質的異常を排除します。
3ピロリ菌検査
血液、尿、便、または内視鏡下での検査で感染の有無を確認します。
4超音波検査
胆石や膵炎など、他の消化器疾患を除外するために行います。
機能性ディスペプシアの治療
機能性ディスペプシアの治療は、症状や原因に応じて個別化されます。
1. 生活習慣の改善
食事指導
- 少量の食事を頻回に摂取する。
- 脂肪分や香辛料、アルコールを控える。
- ゆっくりとよく噛んで食べる。
ストレス管理
ヨガ、マインドフルネス、リラクゼーション法を取り入れることで、自律神経を整えます。
規則正しい生活リズム
十分な睡眠と適度な運動(ウォーキングなどの有酸素運動)が症状緩和に効果的です。
2. 薬物療法
以下の薬が用いられます。
- 酸分泌抑制薬
H2ブロッカーやプロトンポンプ阻害薬(PPI)は胃酸分泌を抑え、心窩部の痛みを軽減します。 - 消化管運動改善薬
モサプリドなどの薬剤が胃の排出を促進します。 - 漢方薬
六君子湯は消化機能を改善し、PDS症状に効果があるとされています。 - 抗うつ薬・抗不安薬
症状がストレスや心理的要因に関連している場合に処方されます。 - ピロリ菌除菌療法
ピロリ菌感染がある場合は、除菌が症状改善につながる可能性があります。
3. 心理療法と行動療法
心理的な負担が強い場合は、認知行動療法(CBT)などを取り入れることで、症状を軽減することができます。
※ 消化器内科の領域ではないため、適切な医療機関をご紹介させていただきます。
機能性ディスペプシアの
予防とセルフケア
機能性ディスペプシアの予防とセルフケアには、生活習慣の改善と適切な食生活が重要です。以下に主な対策をまとめます。
生活習慣の改善
- 規則正しい生活リズムを保つ
- 十分な睡眠をとる
- 適度な運動を行う(ウォーキングなどの有酸素運動)
- ストレス管理を行う(趣味や運動でストレスを発散する)
- 禁煙する
- アルコールは控えめにする
食生活の改善
- 少量の食事を頻繁に摂る
- よく噛んでゆっくり食べる
- 腹八分目を心がける
- 高脂肪食、辛い食品、刺激物を避ける
- 就寝前の飲食を控える
- コーヒーやカフェインの摂取を減らす
その他の注意点
- 過労を避ける
- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の使用を控える
- 胃に負担をかけない食事を心がける
- 食後すぐに運動を行わない
これらの予防法とセルフケアを日常生活に取り入れることで、機能性ディスペプシアの症状の発生や悪化を防ぐことができます。症状が持続する場合は、医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
また、機能性ディスペプシアの患者さんでは、睡眠不足、運動不足、不規則な食事時間やかたよった食事内容など、生活習慣や食習慣が乱れていることがあり、これらを改善することで症状が改善することがあります。
気になる症状があれば、なるべく早めにご相談ください。医療スタッフの適切なサポートを受けながら、生活習慣の改善に取り組むことが大切です。