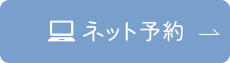下痢とはどのような症状か?
下痢は、通常よりも柔らかく水分を多く含んだ便が頻繁に排泄される状態です。便が水っぽくなるため、排便時に勢いがあることも特徴です。一般的には、1日に3回以上の軟便や水様便がみられる場合に下痢とみなされます。
下痢には、突然始まり短期間で収束する「急性下痢」と、4週間以上持続し慢性的な原因を持つ「慢性下痢」があります。
急性下痢は多くの場合、感染症や一時的な体調不良が原因で、適切な対処をすれば短期間で改善します。一方で、慢性下痢は消化管の炎症や機能の異常、または全身的な病気に起因することが多く、長期間放置すると健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、下痢の頻度や便の状態を観察し、必要に応じて医療機関での診察を受けることが大切です。
受診の目安
下痢は一時的な症状で自然に治ることもありますが、次のような状況に該当する場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
- 脱水症状がみられる場合
下痢が続くと体内の水分や電解質が失われ、口の渇き、めまい、皮膚の乾燥、尿量の減少といった脱水症状が現れます。特に小児や高齢者では、軽度の脱水でも重篤化する可能性があるため注意が必要です。 - 血便や粘液便がある場合
便に血液や粘液が混ざっている場合は、腸内の重篤な炎症や感染症が疑われます。これらの症状は放置せず、医師の診察を受ける必要があります。 - 発熱を伴う場合
38℃以上の発熱がある場合、感染症が疑われるため適切な治療が求められます。 - 症状が長引いている場合 3日以上下痢が続く場合や慢性的に症状がみられる場合は、消化器の疾患が隠れている可能性があります。
- 激しい腹痛がある場合
下痢とともに激しい腹痛が現れる場合は、腸閉塞や急性腹膜炎などの緊急性の高い疾患の可能性もあるため、速やかに受診してください。
下痢の原因と関連疾患
下痢の原因は多岐にわたり、大きく以下のようなカテゴリに分類されます。それぞれの原因に応じて、治療法や対処法が異なります。
1. 感染症による下痢
ウイルス、細菌、寄生虫などが腸に感染すると、腸管の働きが乱れ下痢が起こります。たとえば、ノロウイルスやロタウイルスは、特に冬季に多くみられ、小児から高齢者まで幅広い年代に影響を及ぼします。 また、細菌性の食中毒(サルモネラ菌、カンピロバクターなど)は、不衛生な食品の摂取が原因となることが一般的です。さらに、旅行中に現地の水や食事を通じて感染する「旅行者下痢症」もよく知られています。
2. 食事や薬剤の影響
普段の食事内容も下痢を引き起こす要因になります。辛い食べ物や脂肪分の多い食品は腸を刺激しやすく、過剰摂取すると下痢が起こることがあります。また、人工甘味料(ソルビトールやマニトールなど)を多く含む食品や飲料も腸に影響を及ぼすことがあります。 さらに、抗生物質や一部の薬剤が腸内細菌のバランスを崩し、下痢を誘発することも少なくありません。
3. 消化管の機能異常
過敏性腸症候群(IBS)は、ストレスや不規則な生活習慣が引き金となり、腸の運動や感覚が過敏になることで下痢を引き起こします。これにより、特に食後すぐにトイレに行きたくなる症状がみられることがあります。
4. 炎症性腸疾患
クローン病や潰瘍性大腸炎などの慢性的な炎症性腸疾患は、持続的な腹痛や頻回の水様便、場合によっては血便を引き起こします。これらは長期的な治療が必要で、早期の診断が症状の進行を抑える鍵となります。
5. 栄養素の吸収不良
乳糖不耐症では乳製品を消化するための酵素が不足しており、これが原因で下痢や腹部膨満感を引き起こします。セリアック病ではグルテンを含む食品が腸に炎症を引き起こし、慢性的な下痢の原因となります。
6. 内分泌や代謝の異常
甲状腺機能亢進症では、腸の動きが活発になりすぎることで下痢が生じます。また、糖尿病に関連する神経障害も腸の働きに影響を及ぼすことがあります。
下痢の検査方法
下痢の原因を特定するために、以下のような検査を行います。
- 問診と視診
便の形状や色、粘度などの観察を含め、食事内容や旅行歴、服薬中の薬剤なども確認します。これにより、感染性の可能性や食事の影響などを絞り込みます。 - 便検査
便の培養や寄生虫検査により、細菌や寄生虫の感染を特定します。また、便潜血検査では腸内出血の有無を確認します。 - 血液検査
炎症反応や貧血、電解質異常を調べ、下痢の原因となる全身性の問題を探ります。 - 画像検査
超音波検査やCTスキャンで腸の炎症や腫瘍、機能的な異常を確認します。必要に応じて内視鏡検査も行い、腸内の粘膜状態を詳しく調べます。
下痢の対処方法
- 水分補給
下痢で失われた水分と電解質を補うことが最優先です。経口補水液(ORS)を定期的に摂取し、脱水症状を防ぎましょう。重度の場合は点滴治療が行われることもあります。 - 食事の工夫
消化に優しい食品(おかゆ、スープ、りんごのすりおろしなど)を摂るよう心がけます。乳製品や脂肪分の多い食品、アルコール、カフェインは控えましょう。 - 薬物療法
整腸剤や止瀉薬が症状の緩和に役立つ場合がありますが、感染症が原因の場合は、抗菌薬が必要になることもあります。必ず医師の指示に従って服用してください。 - 原因に応じた治療
例えば、過敏性腸症候群であればストレス管理が重要ですし、炎症性腸疾患には抗炎症薬や免疫調整薬が使用されます。病気の特性に合わせた治療が必要です。
下痢は単なる一過性の不調である場合もありますが、感染症や炎症性疾患など重大な原因が隠れていることもあります。適切な水分補給や食事管理で自然に治る場合も多いですが、症状が続いたり重篤な兆候がみられたりする場合は、早めに医療機関を受診しましょう。自分の症状を正確に伝えることで、より早い診断と適切な治療を受けることができます。