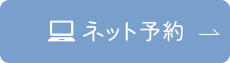血便とは
血便とは、便に血が混じっている状態を指します。血の色や量、便の形状によって、出血の部位や原因を推測することができます。血便は消化管のどこかで出血が起きているサインであり、放置すると病気が進行する可能性があるため、適切な診断と治療が必要です。
血便がある場合の受診の目安
血便の原因は、痔のような軽いものから、大腸がんや炎症性腸疾患など放置できない病気までさまざまです。次のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
すぐに受診が必要なケース
以下のような症状がある場合は、緊急性が高いため、速やかに医療機関を受診してください。
- 便器が真っ赤に染まるほどの大量の出血がある
- 便が黒く、タールのように粘り気がある(上部消化管からの出血の可能性)
- 血便とともに強い腹痛・発熱・嘔吐がある
- 出血に加えて意識がもうろうとする、冷や汗が出る(貧血の兆候)
- 突然血便が出るようになった(特に中高年以降)
- 体重減少や食欲不振が続いている
早めに消化器内科を受診すべきケース
以下の症状がある場合は、緊急ではなくても、できるだけ早めに消化器内科で検査を受けることをおすすめします。
- 少量の血便が続く
- 血便とともに下痢や腹痛が続く
- 便が細くなったり、排便回数が変化したりしている
- 貧血の症状(ふらつき、めまい)がある
- 家族に大腸がんや炎症性腸疾患の人がいる
血便は放置せず、症状の程度に応じて適切なタイミングで受診することが大切です。特に、大腸がんは早期発見・治療が重要なため、気になる症状がある場合は迷わず専門医に相談しましょう。
血便の種類と出血部位の推測
血便は、色や形状によって出血の原因や部位をある程度推測することができます。明るい赤色の血が混ざる場合は、直腸や肛門付近からの出血の可能性が高く、暗赤色の場合は大腸の奥の方、黒色便の場合は胃や十二指腸などの上部消化管での出血が疑われます。
- 鮮血便(明るい赤色の血)
- 暗赤色の血便(ワイン色・レンガ色・黒ずんだ赤色)
- タール便(黒色便)
鮮血便(明るい赤色の血)
鮮血便は、便の表面に血が付着している、または便器の水が赤く染まるような状態を指します。トイレットペーパーにも鮮やかな赤い血が付くことが多く、比較的少量の出血であれば、痛みを伴わずに排便時に気づくこともあります。出血が鮮やかな赤色である理由は、血液が酸素に触れたまま排出されるためであり、出血部位が肛門に近いことを示しています。 このような血便が見られる場合、最も考えられるのは痔(いぼ痔・切れ痔)です。特に切れ痔では排便時に痛みを伴うことが多く、いぼ痔では排便後に滴るように出血することがあります。また、大腸の下部に位置する大腸ポリープや直腸がんも、鮮血便の原因となることがあります。ポリープが大きくなると出血しやすくなり、がんの場合は便が細くなったり、排便後の残便感が続いたりすることがあります。さらに、炎症性腸疾患である潰瘍性大腸炎やクローン病でも、鮮血が混じった粘血便が出ることがあり、これらは慢性的な下痢や腹痛を伴うことが特徴です。細菌感染による腸炎では、血便とともに発熱や強い腹痛が起こることもあります。
鮮血便(明るい赤色の血)
暗赤色の血便は、便全体に血が混じっている場合が多く、鮮血便と比較すると酸化が進んでいるため色が暗めになります。これは、出血部位が腸の奥(大腸の中部や右側)にあることを示唆しており、盲腸や上行結腸、横行結腸などからの出血が考えられます。
このような血便の原因としては、大腸がん(特に右側結腸がん)が疑われます。右側の結腸がんは比較的進行するまで症状が出にくく、血便が見られた時点で進行していることも少なくありません。また、虚血性腸炎では、大腸の血流が悪くなり粘膜が損傷することで出血し、突然の腹痛とともに暗赤色の血便が見られます。さらに、大腸の壁にできたくぼみ(憩室)からの憩室出血も考えられます。この場合、痛みを伴わずに突然大量の出血をすることがあり、高齢者に多く見られます。
細菌感染による細菌性腸炎(赤痢菌・カンピロバクター・腸管出血性大腸菌など)でも、下痢や発熱を伴いながら血便が見られることがあります。特に、腸管出血性大腸菌(O157など)による腸炎では、激しい腹痛や水様性下痢の後に血便が出ることが特徴です。
タール便(黒色便)
タール便とは、便が真っ黒で粘り気があり、アスファルトのような外観をしている血便のことです。通常の便と比較して、生臭い独特のニオイが強くなることが特徴です。これは、血液が消化管を通る間に胃酸や消化酵素によって変化し、酸化することで黒くなるためです。黒色便が見られる場合、出血部位は胃や十二指腸、食道などの上部消化管である可能性が高いです。
このような血便が見られる原因として、最も一般的なのが胃潰瘍や十二指腸潰瘍です。これらの疾患では、胃酸の影響で粘膜が傷つき、出血を起こします。特に空腹時や夜間に強い腹痛が見られることが多く、ピロリ菌感染やストレス、長期間のNSAIDs(痛み止め)の使用が関与していることが多いです。また、胃がんでも黒色便が見られることがあり、進行すると食欲低下や体重減少、貧血症状が出ることもあります。
さらに、食道静脈瘤破裂は、肝硬変などの肝疾患がある患者に見られることが多く、大量の出血を引き起こすことがあります。この場合、黒色便だけでなく吐血を伴うこともあります。嘔吐を繰り返した後に食道が裂けて出血するマロリー・ワイス症候群も、タール便の原因の一つです。
血便の原因
出血の原因は、痔のような良性の疾患から大腸がんのような深刻な病気まで幅広いため、自己判断せずに消化器内科を受診し、適切な検査を受けることが大切です。特に、タール便や突然の大量出血、体重減少や貧血を伴う場合は、早急な受診が必要になります。
血便の原因については、こちらをご覧ください。