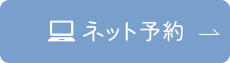急性胃腸炎とは
急性胃腸炎は、胃や腸の粘膜が炎症を起こして突然症状が現れる消化器疾患です。主にウイルスや細菌などの病原体が原因となり、嘔吐、下痢、腹痛、発熱が見られます。特に感染性胃腸炎が多く、食事や水の汚染、接触感染が原因となることが一般的です。
多くの場合、急性胃腸炎は1~3日で自然に回復しますが、症状が強い場合や長引く場合には注意が必要です。特に脱水症状が進行すると重篤化するリスクがあるため、水分補給を徹底することが重要です。
急性胃腸炎の原因と感染経路
ウイルス性胃腸炎
ウイルスが胃腸の粘膜に感染し、炎症を引き起こします。主に冬季に流行し、特に乳幼児や高齢者で重症化することがあります。ウイルス性胃腸炎はノロウイルスやロタウイルスが主な原因です。これらのウイルスは食品や水、感染者の嘔吐物や便を介して感染し、飛沫感染する場合もあります。水様性下痢が主症状で、嘔吐や軽度の発熱を伴います。通常、1~3日で自然に回復しますが、脱水に注意が必要です。急性胃腸炎は原因によって症状や治療法が異なるため、適切な診断と治療が重要です。特に症状が重い場合や長引く場合は、速やかに医療機関を受診してください。
ノロウイルス
冬に多発し、非常に感染力が強いのが特徴です。感染者の嘔吐物や便、汚染された食品や水を介して感染します。症状は突然の嘔吐、下痢、腹痛が特徴です。
ロタウイルス
乳幼児に多く、白色便を伴う激しい下痢が見られます。ワクチン接種により、重症化を予防できます。
アデノウイルス
年中発症が見られ、小児に多い胃腸炎です。水様性下痢が1~2週間続くことがあります。
細菌性胃腸炎
細菌性胃腸炎は細菌そのもの、または細菌が産生する毒素が胃腸の粘膜に影響を及ぼします。夏季に多く、サルモネラ菌や腸管出血性大腸菌(O157)などが原因です。これらは食品の汚染によって広がり、血便や高熱を伴うことがあります。細菌の毒素が原因の場合、食後数時間以内に症状が現れ、嘔吐や下痢が突然発生します。重症化すると腸管の損傷や全身感染症を引き起こします。
腸管出血性大腸菌
(O157など)
生肉や汚染された野菜が原因です。激しい腹痛や血便が特徴で、溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすことがあります。
サルモネラ菌
加熱不十分な卵や鶏肉が原因です。38~39℃の高熱と下痢が見られます。
カンピロバクター
生や加熱不十分な鶏肉が原因です。発症までの潜伏期間が長く、腹痛や発熱が特徴です。
腸炎ビブリオ
生魚や刺身などの海産物が原因です。短時間で激しい下痢や腹痛が現れます。
急性胃腸炎の主な症状
急性胃腸炎の症状は原因(ウイルス、細菌、毒素、非感染性など)によって異なりますが、共通して胃や腸の粘膜の炎症に起因する次の症状が見られます。
急性胃腸炎の症状は、感染や炎症が進むにつれて次のように進行します:
- 初期段階:腹部不快感、軽い下痢や嘔吐。
- 中期段階:頻回の下痢と嘔吐、発熱や腹痛が加わる。
- 重症段階:脱水症状、意識障害、血便など。
医療機関を受診すべき
場合
以下の症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診してください:
- 3日以上続く下痢や嘔吐。
- 血便や黒色便。
- 高熱(39℃以上)。
- 尿量の減少や意識障害。
- 小児、高齢者、免疫不全患者の症状が進行している場合。
※ 3日以上の症状継続だけでなく、症状の重症度や患者の年齢、基礎疾患によっても受診の必要性が変わります。早めにご相談ください。
急性胃腸炎の症状は多岐にわたりますが、早期の対応が回復を早める鍵です。特に脱水症状に注意を払い、適切な水分補給と医師の診断を受けることが重要です。
1. 下痢
下痢は最も一般的な症状で、原因によって水様性から粘血便まで異なります。
- ウイルス性:水様性便が多く、臭いが強い。
- 細菌性:粘液や血液を含むことがあり、特に腸管出血性大腸菌(O157)では血便が見られる。
- 毒素性:急激に発症し、水のような下痢が特徴。
1日に数回から10回以上に及ぶことがあり、体力の消耗や脱水を引き起こします。
2. 嘔吐
嘔吐は特にウイルス性胃腸炎で顕著で、小児に多く見られます。突然始まり、数回繰り返されることが一般的です。食事や水分を摂取してもすぐに吐いてしまうことがあります。
通常、1~2日で収まりますが、個人差があり、より長引くことがあります。
3. 腹痛
腹痛は腸管の痙攣による痛みが多く、波のように強くなったり弱くなったりするのが特徴です(腹痛は必ずしも波状的ではなく、持続的な痛みを感じる場合もあります)。腹部全体に広がる痛みや、下腹部を中心とした痛みが見られます。「差し込むような痛み」「鈍い不快感」と表現される患者さんが多いです。
細菌性胃腸炎では、強い痛みを伴うことがあります。
4. 発熱
ウイルスや細菌が感染の原因となる場合、発熱が見られます。
- ウイルス性:37~38℃程度の軽い発熱が多いですが、ウイルス性胃腸炎でも39℃以上の高熱が出ることがあります。
- 細菌性:39℃以上の高熱を伴うことがあり、場合によっては悪寒も見られます。
注意:高熱が長引く場合や、他の症状が強い場合は医師の診断が必要です。
5. 脱水症状
脱水症状は頻回の下痢や嘔吐により体内の水分と電解質が失われることで発症します。
- 軽度の症状:
・口の渇き、尿量の減少。
・倦怠感、軽いめまい。 - 重度の症状:
・強い倦怠感、意識障害、泣いても涙が出ない(小児の場合)。
・皮膚の弾力低下(つまんだ皮膚が元に戻らない)。
※ 症状が悪化する前に、なるベく早めにご相談ください。
6. 血便
細菌性胃腸炎に特有で、腸管の炎症が進んだ場合に見られることがあります。 腸管出血性大腸菌(O157)や赤痢菌が原因の場合、血液が混じった便が特徴です。
注意:血便は重症のサインであり、速やかな医療機関の受診が必要です。
7. 倦怠感と食欲不振
体内のエネルギー消耗や脱水、炎症によるものです。食欲不振が顕著で、無理に食事を摂取することで嘔吐が悪化することもあります。
※ 日常生活に支障をきたす前に、早めに受診してください。
8. その他の症状
- 頭痛:脱水症状や発熱に伴い、頭痛が起こることがあります。
- 筋肉痛:発熱を伴うウイルス感染時にみられることがあります。
必ずしも全ての急性胃腸炎患者に見られるわけではありません。
急性胃腸炎の
検査・診断方法
診断は問診、便検査、血液検査を基に行われます。問診では発症したタイミングや食事の内容、周囲で似た症状を持つ人がいるかを確認します。便検査でウイルスや細菌を特定し、血液検査では炎症や脱水の程度を評価します。症状が重い場合や血便が見られる場合には、画像検査(超音波やCT)を用いて他の疾患との鑑別を行います。
1問診
問診では、患者さんの症状の特徴や発症経過を確認し、原因や感染経路を推測します。具体的には以下の項目を確認します:
- 症状の経過(発症時期、症状の強さ、持続時間)。
- 最近食べた食品や水分摂取の状況(特に生ものや外食の有無)。
- 海外旅行歴や特定の地域への訪問歴(特に衛生状態が悪い地域)。
- 家族や周囲で同様の症状を持つ人がいるか(集団感染の可能性)。
2便検査
便のサンプルを採取し、病原体の特定を行います。
- ウイルス検査:ノロウイルスやロタウイルスなどを迅速診断キットで検出。
- 細菌培養検査:サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌(O157)、カンピロバクターなどの特定。
- 寄生虫検査:クリプトスポリジウムやジアルジアなど、特定の寄生虫を検出する場合。
※ 便検査の結果は原因に応じて数時間から数日かかることがあります。
3血液検査
血液検査は症状の重症度を評価するために行われます。
- 炎症反応:C反応性蛋白(CRP)や白血球数を測定し、体内の炎症の程度を確認します。
- 電解質バランス:脱水症状や電解質異常(ナトリウム、カリウム濃度など)を確認します。
- 腎機能:重度の脱水では腎機能が低下するため、血清クレアチニン値や尿素窒素を評価します。
4画像検査(必要に応じて)
血便や激しい腹痛がある場合、他の疾患との鑑別を行うために画像検査を実施することがあります。
- 腹部超音波:腸管の炎症や腫れ、その他の異常を確認します。
- CT検査:腸閉塞、腸管穿孔、炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)との鑑別します(協力医療機関をご紹介させていただきます)。
急性胃腸炎の治療方法
軽症の場合は自宅療養が基本です。最も重要なのは水分補給で、経口補水液を用いて体内の水分と電解質を補います。食事は無理に摂らず、消化に優しいお粥やスープなどを少量ずつ摂取します。整腸薬が腸内環境の改善に役立つこともありますが、自己判断での使用は避けるべきです。
重症例では医療機関での治療が必要です。嘔吐や下痢が続き、経口で水分摂取が難しい場合は点滴で水分や電解質を補充します。細菌性の場合は原因菌に応じた抗菌薬を使用することがあります。
急性胃腸炎の治療は、原因や症状の重症度に応じて異なります。多くの場合、軽症では自然治癒しますが、症状の軽減や合併症の予防のために適切な治療が必要です。以下に、治療方法を詳細に説明します。
対症療法
急性胃腸炎の多くはウイルス性であり、特定の治療薬がないため、症状を和らげることが治療の中心となります。
水分補給(脱水予防)
嘔吐や下痢で失われた水分と電解質を補うことが最優先です。
方法:
- 軽症の場合:経口補水液(ORS、OS-1など)を少量ずつ頻回に摂取します。
- 嘔吐が激しい場合:数分ごとに小さじ1杯程度から始め、徐々に量を増やします。
- スポーツドリンクや家庭の水分も代替可能ですが、塩分や糖分が適切でない場合があるため注意が必要です。
中等症~重症の場合:
経口摂取が難しい場合は、医療機関で点滴を行います。
食事療法
症状が落ち着くまでは無理に食べないことが大切です。嘔吐や下痢が治まってから、消化に優しい食事を少量ずつ摂取します。
おすすめの食品:
- お粥、うどん、りんごのすりおろし、スープなど。
避けるべき食品:
- 脂肪分が多い食品、乳製品、カフェイン、アルコール、辛いもの。
薬物療法
- 整腸薬:
腸内環境を整える乳酸菌製剤やビフィズス菌製剤が有効な場合があります。 - 制吐薬:
嘔吐が激しい場合には、制吐薬を使用することがあります。ただし、小児では慎重に使用します。 - 解熱薬:
発熱が高い場合や、発熱に伴う不快感が強い場合に使用されます。アセトアミノフェンが一般的です。
原因に応じた治療
ウイルス性胃腸炎
- 特定の治療薬はなく、対症療法が中心です。
- 脱水予防と症状の緩和に重点を置きます。
細菌性胃腸炎
抗菌薬の使用:
- 腸管出血性大腸菌(O157)や軽症のサルモネラ菌感染では、抗菌薬の使用は推奨されない場合があります。菌を完全に排出させることが重要です。
- 重症例(敗血症や重篤な感染症の場合)では、適切な抗菌薬を選択して治療を行います。
注意:
抗菌薬の使用は、必ず医師の指示のもとで行います。
毒素性胃腸炎
- 主に対症療法が中心です。発症の原因となった食品を特定し、同様の症状が他者にも見られる場合は集団感染の可能性を報告します。
寄生虫性胃腸炎
毒素性胃腸炎
- クリプトスポリジウムやジアルジアが原因の場合、特定の抗寄生虫薬を使用します。
非感染性胃腸炎
- 原因物質(薬剤、アレルゲン、化学物質)を特定し、それを除去することが治療の基本です。
特別な場合の治療
小児の場合
- 小児は脱水の進行が早いため、特に注意が必要です。
- 経口補水液をこまめに摂取し、嘔吐が続く場合は早期に医療機関を受診します。
- 小児で下痢止め薬は推奨されません。
高齢者の場合
- 高齢者は腎機能低下や免疫力の低下により、症状が重症化しやすいです。
- 点滴による補水が必要になる場合があります。
- 合併症を防ぐために早期の医療機関受診が重要です。
急性胃腸炎の予防と対策
急性胃腸炎はウイルスや細菌、毒素などによって引き起こされるため、感染の防止と原因の特定が予防の鍵となります。
急性胃腸炎の予防には、手洗いの徹底、食品の適切な管理、感染者との接触回避が特に重要です。また、家庭内での感染拡大を防ぐための衛生管理や、乳幼児へのワクチン接種も有効です。日常生活での衛生意識を高め、早期対応を心がけることで、発症や重症化のリスクを最小限に抑えることができます。
1. 手洗いの徹底
手洗いは、ウイルスや細菌の拡散を防ぐ最も基本的かつ効果的な方法です。特にノロウイルスなどの感染力が強いウイルスに対して有効です。
正しい手洗いの方法
- 流水と石鹸を使い、20秒以上かけて指先、爪、指の間まで丁寧に洗います。
- トイレの使用後、食事の前後、調理の前後、感染者の世話をした後には必ず手を洗います。
- アルコール消毒は補助的に使用しますが、ノロウイルスには効果が限定的であるため、石鹸による手洗いが優先されます。
2. 食品の適切な管理
食品の加熱
食材は十分に加熱(中心温度75℃以上で1分以上)し、生肉や魚介類は適切に調理します。特にカンピロバクターや腸炎ビブリオなどの細菌性胃腸炎は、不十分な加熱が原因となることが多いため注意が必要です。
食品の保存
調理後は速やかに冷蔵庫で保存し、常温で長時間放置しないようにします。冷蔵庫内でも、生肉や魚を生で食べる食品(サラダなど)と分けて保存します。
食品の取り扱い
生肉や魚に触れた調理器具(包丁、まな板)や手は、使用後すぐに洗浄・消毒します。生食用と加熱調理用の調理器具を分けることが推奨されます。
3. 感染者との接触を避ける
感染者の嘔吐物や
便の処理
- 嘔吐物や便は、次亜塩素酸ナトリウム(0.1~0.5%濃度)で消毒します。
- マスクと手袋を着用し、処理後は必ず手を洗います。
タオルや食器の共有を
避ける
- 感染者とタオルや食器を共有せず、感染が広がらないよう個別に使用します。
感染者の隔離
感染力が高いウイルス(ノロウイルスなど)の場合、可能な限り感染者を隔離し、接触を最小限に抑えます。
4. ワクチン接種
ロタウイルスワクチン
- 乳幼児に有効で、ロタウイルスによる急性胃腸炎の重症化を防ぎます。
- 生後2か月から定期接種が可能で、適切なタイミングで接種することで有効性を最大化できます。
5. 環境の衛生管理
感染者が使用したトイレや調理場は、次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、汚染の拡大を防ぎます。嘔吐物や便が付着した衣類やリネンは、熱湯(85℃以上)で洗濯するか、消毒剤を使用します。
6. 健康管理と免疫力の
向上
バランスの取れた食事
- 免疫力を高めるために、栄養バランスの良い食事を心がけます。特に、腸内環境を整える発酵食品(ヨーグルト、味噌、納豆など)を積極的に摂取します。
十分な睡眠と適度な運動
- ストレスを軽減し、免疫機能を正常に保つために重要です。
水分摂取
- 脱水を防ぐために、日頃から適切な水分摂取を心がけます。